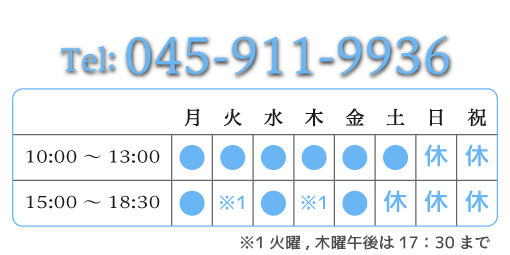不妊の原因
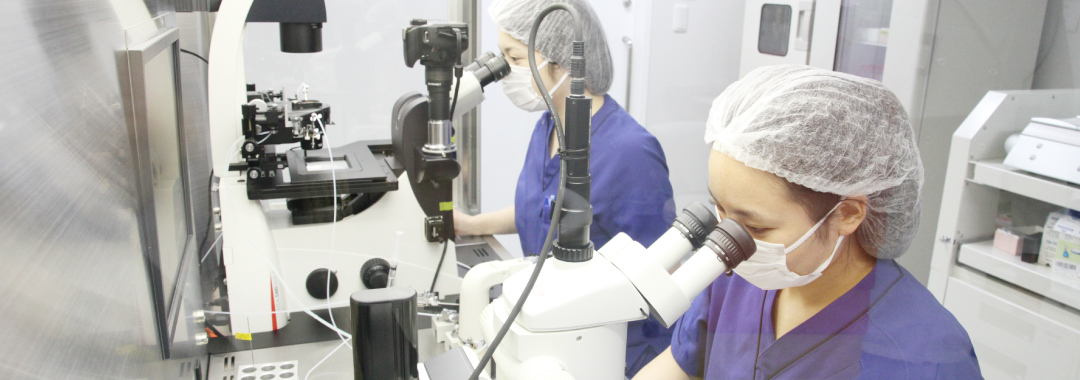
不妊の原因は人それぞれです
避妊をせず、夫婦が普通に性生活を続けると、1年で80%、2年で90%のカップルが妊娠しますが、残念ながら10%の方は、なかなか妊娠に至りません。
日本では、健康な夫婦が1年以上妊娠しなかった場合を、不妊症と定義しています。
しかし、赤ちゃんが欲しい、という願いの強さは人それぞれです。
「妊娠できる身体でしょうか」
「妊娠しにくい気がするのですが」
「原因を調べて欲しい」
「一日でも早く妊娠したい」
と、思いは皆さん違いますね。
必ずしも1年経たなくても、1日も早く赤ちゃんをその手に抱きたい、その気持ちを尊重し、必要な検査、必要な治療を一緒に考えていきましょう。
また、1年以上妊娠しなければ、というのも一般論であって、35歳以上の方はなるべく早く、また子宮内膜症や子宮筋腫がある方も1年のうちに病気が悪くなるかも知れませんから早くに受診することを勧めています。
また、「不育症」という、妊娠はできるけれど、初期の流産を繰り返し、 お産に至らない場合もありますが、不妊症と同様に、検査、治療法を考えていきたいと思います。
※WHO(世界保健機関)が不妊症のカップルに行った調査では、不妊の原因が女性だけにある場合が41%、 男性だけにある場合が24%、男女両方にある場合が24%でした。
- 排卵因子
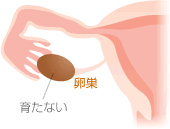 ホルモンバランスなどに問題があるため卵胞が育たない、排卵が起こらない。
ホルモンバランスなどに問題があるため卵胞が育たない、排卵が起こらない。
原因となりうる疾患① 多のう胞性卵巣症候群(PCOS)
月経不順や排卵障害、無月経の原因の中で、最も多い疾患です。
海外では主に肥満の方にみられますが、日本では標準体重の方や痩せている方にも多くみられます。
また男性ホルモンの分泌が多いこともあり、多毛症状やニキビ・肌荒れに悩んでいる方もいらっしゃいます。
他にも糖尿病やインスリン抵抗性、 甲状腺機能低下症を合併していることがあります。
治療法として排卵誘発剤やインスリン抵抗性改善薬、男性ホルモン作用を下げる薬が用いられます。
詳しくはこちらのページで解説していますのでご確認ください。原因となりうる疾患② 高プロラクチン血症
脳の一部、下垂体から産生される乳汁分泌ホルモンで、本来は授乳中に活発に産生され、母乳を作り出します。時に妊娠していないのに乳汁が出る、乳漏症から発見される場合もあります。
服用している薬剤や下垂体腫瘍が原因であることもありますが、特発性とされる原因不明の場合が多いです。
プロラクチンは排卵障害の原因になるだけでなく、排卵される卵子の質を低下させると言われて
います。
MRIで下垂体性腫瘍を否定することが重要ですが、治療はドーパミン作動薬(カバサール、テルロンなど)の内服が必要です。原因となりうる疾患③ 下垂体機能不全
排卵障害の中では重い病態で、下垂体を刺激する視床下部の障害と鑑別診断する必要があります。
下垂体が原因の場合、排卵するにはHMGやFSHなどの注射剤を毎日用いる必要があります。
(下の、視床下部機能不全と併せて「中枢性卵巣機能不全」と呼ばれます)原因となりうる疾患④ 視床下部機能不全
下垂体を刺激する、より上位中枢の組織で、急激なダイエットや過度の運動負荷が原因となることがあります。
最近では女性アスリートの無月経問題がクローズアップされています。原因となりうる疾患⑤ その他の排卵障害
卵胞発育不全
上のような明らかな原因がなくても排卵しにくい、排卵しないことはあります。
また、ほかにも以下の障害があります。
遅延排卵
卵胞は発育するものの、月経から排卵まで時間がかかるため、月経周期が長くなります。詳しくはこちらをご覧下さい。
LHサージ遅延・LHサージ不全
排卵する前日に、LHというホルモンが下垂体から放出され、LHサージと呼ばれますが、このLHサージがなかなか起こらなかったり(LHサージ遅延)、起こらない(LHサージ不全)ために排卵しない病態があります。
治療はLHとよく似ているHCGというホルモン剤を注射するだけなので、難しくはありません。未熟排卵
卵子が未熟なままで排卵する病態で、ほとんど妊娠することはありません。主に年齢が若く卵巣の働きが未成熟であったり、反対に加齢変化とともにみられます。治療として排卵誘発剤で卵巣を刺激します。
過熟排卵
LHサージが起こる際に、卵子が過熟している状態です。卵子は未熟から成熟に至った時に排卵されるのがベストですが、その後、過熟になると妊娠率が低下します。これも年齢とともにみられるようになります。治療は上のLHサージ不全と同様、卵子が過熟になる前にHCG製剤を注射します。
LUF(黄体化未破裂卵胞症候群)
LHサージやHCG製剤の投与によっても卵胞が破裂しない病態です。卵巣周囲の癒着や高プロラクチン血症などが原因と考えられています。
詳しい解説はこちらをご覧下さい。原因となりうる疾患⑥ 加齢変化
年齢とともに卵子の質が低下することが知られており、主な不妊の原因となります。また若い方でも早いうちに卵巣の機能が悪くなり、良い卵子が作れなくなってくることもあります。根本的な治療はなく、なるべく早く妊活に取り組むこと以外に有効な方法はありません。思い立った時に相談にいらしていただきたいと思います。
原因となりうる疾患⑦ 早発卵巣不全
40歳に至る前に閉経と同じように卵巣の働きが停止する病態です。染色体の異常がある場合もあります。
エストロゲン・プロゲスチン療法と呼ばれるホルモン治療を行うことで、卵巣が再度働く場合があります。原因となりうる疾患⑧ 甲状腺疾患
主に橋本病などの甲状腺機能低下症で、排卵障害や不妊、流産となることがあり、また妊娠した後も赤ちゃんへの影響などがあるため妊娠前に甲状腺の治療を開始することが必要な場合があります。
その他の卵巣機能障害黄体機能不全
排卵後、着床を促す黄体ホルモンの分泌が少ないために起こります。高温期の体温が上昇しない、高温期が短い、高温期に子宮内膜が厚くならない、高温期に不正出血がみられる、といった症状が現れることもあります。治療は黄体ホルモン製剤を内服します。詳しくはこちらで解説しています。
- 卵管因子(卵管性不妊)
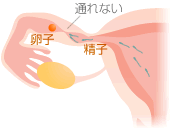 卵管がつまっていたり、卵管が周囲の臓器と癒着したりしているために卵子と精子が出会えず、受精が出来ません。
卵管がつまっていたり、卵管が周囲の臓器と癒着したりしているために卵子と精子が出会えず、受精が出来ません。
原因となりうる疾患① 感染による炎症
感染には様々な原因菌がありますが、最も多いのがクラミジア感染です。 他に淋菌や一般細菌によるものがあります。
これらは骨盤腹膜炎、骨盤内感染、PIDと呼ばれる病態を引き起こすことが多いです。PIDは、発熱を伴う下腹痛があり、内科的な腹痛と間違われることもあります。
いずれの感染でも、感染により炎症が引き起こされ、その結果卵管や卵巣が癒着し、さらに子宮や腸、骨盤の壁に癒着することがあります。
原因となりうる疾患② 子宮内膜症子宮内膜症による卵管因子は、こちらの「子宮内膜症」を解説したページをご覧ください。
原因となりうる疾患③ 術後癒着子宮筋腫核出術や卵巣のう腫摘出術、帝王切開など、他には虫垂炎、鼠径(そけい)ヘルニアなどの手術の後に、起こることがあります。
術後癒着は必ず起こるものではありません。 全く癒着が無い場合も、またひどい癒着が起こってしまうこともあります。
一般には開腹手術で強く、腹腔鏡下手術では軽い、また癒着はアレルギー体質の方に強く起こる傾向があります。術後の癒着を来たさないよう、手術終了時に癒着防止剤を使うことが多く、これは完全に癒着を防げるわけではありませんが使わない場合に比べて明らかに癒着は軽くなります。
- 子宮因子
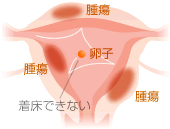 子宮にできた腫瘍や子宮の形に問題があることなどが原因で、受精卵が着床できない。
子宮にできた腫瘍や子宮の形に問題があることなどが原因で、受精卵が着床できない。
原因となりうる疾患① 子宮筋腫
原因となりうる疾患② 子宮内膜ポリープ
原因となりうる疾患③ 子宮腺筋症
原因となりうる疾患④ 子宮内膜菲薄化(子宮内膜が薄くなる)
子宮内膜は、受精卵が着床するところです。受精卵のベッドの役割である内膜が薄いと受精卵が着床しません。
原因は上に書いた黄体機能不全や、子宮血流の障害、中絶や流産などの子宮掻爬手術です。
治療は黄体ホルモン製剤やエストロゲン製剤、血流改善効果のあるビタミンEやビタミンC製剤が用いられますが、治療効果がみられない場合は、生殖補助医療の適応となります。詳しくはこちらで解説しています。
- 頸管因子
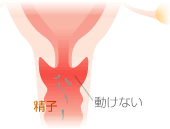
原因となりうる疾患① 頸管粘液の減少
加齢変化でもみられますが、原因不明のことが多いです。クロミッドなどの排卵誘発剤でもみられることがあります。人工授精の適応となることがあります。
原因となりうる疾患② 抗精子抗体精子の動きを妨げる抗体が産生されている場合があります。人工授精でも妊娠できる可能性がありますが、生殖補助医療(体外受精など)による治療が有効です。
- 卵巣因子
- 卵巣の加齢変化に伴う不妊原因で、近年とても多くなっています。
原因となりうる疾患① 加齢変化
- 男性因子
- 不妊の半数近くは男性が原因とされ、その多くは精液所見の異常によるものです。
精液検査で診断しますが、検査では精液の量、精子の濃度、精子の運動率をみます。特に重要なのは運動の速度が速く、直進運動する精子の濃度です。
当院ではこの総数を計算して治療方法を提示しています。精子の所見にもよりますが、多くはサプリメントなどを服用し、改善する方法をお勧めしています。
精液検査についての詳しい情報はこちら>>
- 性交障害
- 性交障害には、 ・性交できるが射精に至らない ・勃起やマスターベーションは出来るが性交が出来ない ・勃起が出来ない(ED) と言った病態に応じた治療法が必要です。神経損傷によるED治療は、専門施設の受診が必要です。