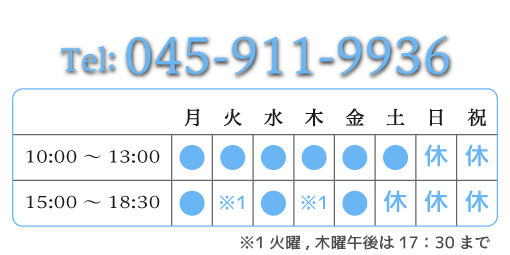この記事の目次
多のう胞性卵巣とは?
生理不順には、さまざまな原因がありますが、最も多い原因の一つが、「多のう胞性卵巣(多囊胞性卵巣症候群、PCO、PCOS)」です。
月経が来なかったり (無月経)、月経が不順であったり。
極端な方だと、半年から1年くらい、月経が来ない方もいらっしゃいます。
排卵しないために不正出血が続くこともあります。
多のう胞性卵巣、なんて言われたら、卵巣に何か病気が出来てしまったのではないか、悪い病気ではないか、と心配してしまうかもしれません。
この病名は、卵巣に小さな、のう胞(袋状の部分)が卵巣にたくさんできてしまったような形から、そのような病名となったのです。
症状の主体は排卵障害ですが、妊娠成立した後でも、流産率が高いとされています。
また肥満がみられることもあります。

多のう胞性卵巣の診断
現在では超音波所見だけでは多嚢胞性卵巣症候群との診断とはならず、ホルモン採血をして確定診断とします。
令和5年に発表された再診の日本の多囊胞性卵巣症候群の診断基準(2024)では、
1. 月経周期異常
2. 多囊胞性卵巣 または AMH高値
3. アンドロゲン過剰症 または LH高値
と改められました。
ホルモン検査の特徴は、
・LHが正常より高い(≧7.1)、LHがFSHより高い(≧1.21倍)
・テストステロン(男性ホルモン)が高い
・AMH(抗ミュラー管ホルモン)が高い
(29歳までは4.4以上、30歳以降は3.1以上)
と定められていますが、検査会社で採用している測定試薬によって異なるので、医療機関によって診断に用いる値が異なります。
欧米では診断基準に「肥満」も含まれますが、日本人の多のう胞性卵巣では肥満の方は決して多くありません。
LH、FSHはともに下垂体から分泌され、本来は卵巣を刺激して排卵を起こすホルモンです。多嚢胞性卵巣では、例えば、LHが15、FSHが5、のように、LH>FSHとなったバランスの悪さが、排卵を起こしにくくさせます。
テストステロンは男性ホルモンのため、女性の卵巣機能に反対の作用をもたらし、すなわち排卵しにくくなるのです。
テストステロンが厄介なのは、男化作用を持つことです。もともと男性ホルモンですから、女性の身体も男性らしくさせます。よくみられる症状が、ニキビ・肌荒れと多毛です。男化作用も排卵障害、月経不順と同じ様に、治療が可能です。
多のう胞性卵巣の追加検査
多囊胞性卵巣症候群では、インスリン抵抗性と甲状腺機能低下症がみられることがあります。
インスリン抵抗性とは、糖尿病に近い病態で、本来血糖値を下げるインスリンというホルモンが、血糖値を下げられない状態です。
この検査は空腹時に血液検査を行うため、朝食を摂らないで午前の外来で採血することを勧めます。
また、甲状腺機能の低下は、月経不順や流産の原因にもなるため、やはり血液検査を行います。
インスリン抵抗性には、下記の治療法のうち、メトフォルミンの内服を、また甲状腺機能の異常は専門医を紹介します。
多のう胞性卵巣の治療法
若年者(まだ赤ちゃんを考えていない年代)とそろそろ赤ちゃんを考えている、いますぐに妊娠を考えている方では治療の考えが異なりますが、ともに肥満のある方には第一に減量が勧められます。減量によって排卵・月経不順が回復し、妊娠率も向上します。
そろそろ赤ちゃんを考えている方、だいたい1年くらい前には、きちんと排卵できるよう、治療に取り組まなければなりません。
妊娠を希望している方の治療法
多嚢胞性卵巣、略してPCOSは、排卵障害を主体とする病気で、そのため月経不順、無月経、無排卵、不妊症など、様々な女性のトラブルの原因となります。
不妊治療では、いろいろな種類の医薬品が用いられますが、その代表はクロミッド(クロミフェンクエン酸塩)で、これまでPCOS以外の排卵障害を含めた不妊治療に、最も多く服用されています。
また特に肥満のある多のう胞性卵巣で有効とされている排卵誘発法に、フェマーラ®︎(レトロゾール)があります。
さて、クロミッドの効果は人それぞれで、効果が弱い方から、反対に卵巣が過剰に刺激されてしまう方もあります。どちらも困るのですが、効果の低い場合は、つまり排卵をしないこと。これでは妊娠することが出来ません。
当院では、
・男性ホルモン(テストステロン)が高い場合=アルダクトン
・インスリン抵抗性がみられる場合=メトフォルミンまたはグリスリン
・他に柴苓湯(さいれいとう)や温経湯(うんけいとう)という漢方薬
・ビタミンD不足の方が多く、ビタミンDが低い方=ビタミンDサプリメント
などを併用する方法で、排卵誘発剤の効果を高めようと工夫していますが、なかなか効果がみられないことがあります。
これらの内服による排卵誘発、また併用療法の効果がない場合、注射剤による排卵誘発を行う必要があります。
注射剤は、HMGやFSHという種類の薬剤を、基本的には連日注射しなければなりません。自己注射できる製剤は「ゴナールエフペン」があります。
しかし、排卵誘発の副作用である、排卵誘発効果が強すぎてしまう卵巣過剰刺激症候群は、注射剤で起こりやすく、また双子以上の妊娠を多胎妊娠と呼びますが、卵胞が2つ以上、時には10〜20個できてしまうこともあり、この場合はたくさんの卵胞ができても、1つだけ子宮に胚移植できるメリットがあるため、生殖補助医療へのステップアップをお勧めします。
上記のようにクロミフェンが効かない状態を、「クロミフェン抵抗性」と呼びますが、PCOS患者さんにクロミフェンとコエンザイムQ10を併用効果がエジプトで発表されました。
この併用効果で改善されたのは、
・発育卵胞数の増加(高度生殖医療では有用です)
・子宮内膜が厚くなる(クロミフェンの副作用で内膜が薄くなることがあります)
・排卵率の上昇
・妊娠率の上昇
が報告されました。
また、PCOSでは肥満が合併することがあり、肥満のPCOSの方がクロミフェン抵抗性の強いことが多いですが、この併用法では肥満の有無にかかわらず効果がみられたそうです。
クロミフェン抵抗性の場合、クロミフェンの服用量を増やしますが、増やすと子宮内膜が薄くなってしまう副作用が出ることがあります。
またクロミフェンを増量しても排卵しない場合は、hMGとかFSHといった注射剤の排卵誘発剤が必要になりますが、コストや通院回数も増えてしまいます。
さらにPCOSの問題として、クロミフェンを増量したり注射剤を用いたり、と卵巣刺激を強めて行くと、ある一定の強さから過剰に反応する、卵巣過剰刺激症候群の発症リスクがあります。もちろん、多胎妊娠のリスクもです。
このため、タイミング法など一般生殖医療での治療が難しく、体外受精など生殖補助医療(高度生殖医療)にステップアップすることも少なくありません。
コエンザイムQ10
抗酸化作用を持つビタミン様の物質、コエンザイムQ10の併用は、誘発剤効果を高めることが期待でき、つまり弱い刺激でも排卵させることが出来るかも知れません。
当院で扱っているサプリメントでは、コエンザイムQ10は「還元型コエンザイムQ10」に200mg含まれています。コエンザイムQ10は脂肪燃焼効果もあるため、肥満の方には一石二鳥です。

グリスリン
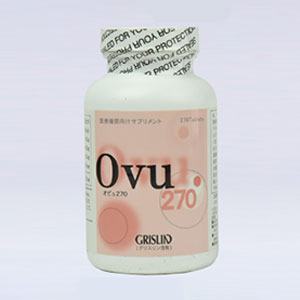 グリスリンの原料はなんと舞茸です。舞茸に含まれた成分で、名前も似ている血糖を下げるホルモン「インスリン」と作用が似ています。
グリスリンの原料はなんと舞茸です。舞茸に含まれた成分で、名前も似ている血糖を下げるホルモン「インスリン」と作用が似ています。
実際に内科の領域では、グリスリン摂取によって、血糖値が下がったり、体重が減少したり、効果が認められています。
婦人科では、特に「多嚢胞性卵巣(PCOS)」の方への有用性が認められています。
排卵障害のある多嚢胞性卵巣の方が用いると、排卵が出来るようになったり、排卵誘発剤を減量できる可能性があります。
この効果は当院で服用されている方でも実際に認められていますし、また当院では高度生殖医療で不良胚ばかり回収されていた患者さんで良好胚が得られるようになり、妊娠、出産に繋がっている方もいらっしゃいます。
生殖補助医療
多囊胞性卵巣の方は、上に述べてきたように治療が難しい排卵障害をが見られることがあります。
一般不妊治療で排卵誘発を行うには限界がありますが、生殖補助医療のように、たくさんの卵胞が発育しても、1つの受精卵を子宮に戻す胚移植を行うことは多囊胞性卵巣の不妊治療として、理想的な治療ともいえます。
なかなか治療効果が見られない場合、生殖補助医療へのステップアップも検討してください。
生殖補助医療の保険診療で行う方法と、治療成績を紹介した動画です。 治療の参考にしてください。
初出:令和2年6月11日
補筆修正:令和2年6月17日、7月9日
補筆修正:令和3年2月17日
補筆修正:令和4年2月24日、5月15日、12月24日
補筆修正:令和5年2月12日、12月16日
補筆修正:令和6年1月8日、2月1日、24日、4月3日、30日
補筆修正:令和7年5月7日、生殖補助医療の治療成績を新しいものに差し替えました。