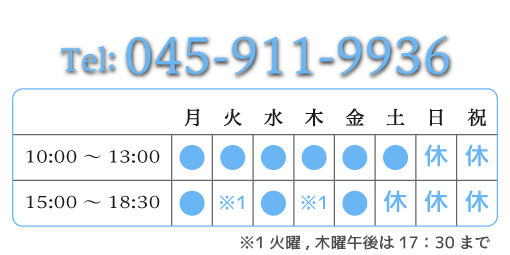リンゴ病、ほほが赤くなることからそう呼ばれている「伝染性紅斑」。
横浜市では9/22~9/28現在、再度患者報告数が増えており、特に緑区では6.25と数多い報告がありました。
当院を受診する患者さんの中にも、お子さんの幼保育園で流行している、と心配されて受信する方がいらっしゃいます。
現在感染が懸念されているのは、インフルエンザ、コロナ、そしてリンゴ病です。
りんご病は保育園や幼稚園を中心に、小さなお子さんたちの病気、と思われがちですが、大人でももちろん感染します。
特に心配しなければならないのが、妊婦さんたち。
妊婦さんが伝染性紅斑に罹ると、お腹の赤ちゃんに感染し、最悪の場合は胎児死亡となります。これは比較的頻度が高く、当院でも過去の流行で、数名の妊婦さんが感染してしまい、残念ながらお腹の赤ちゃんが亡くなってしまうケースも複数ありました。
・胎児への感染は、ほとんど(9割)が母体感染の1〜8週間以内に発症します。
・妊娠20週未満の感染例では、20週以降に比べて胎児死亡率が高くなります。胎児死亡率は8.2%との報告があります。
・胎児に感染しても、1/3は自然寛解します。
・胎児が感染した場合、胎児水腫を来たします。妊婦さんが感染すると11.4%、胎児水腫となります(Xiong Y et al. 2019)。
・胎児の所見が消失すれば、感染しなかった赤ちゃんと同じ経過となり、心配は不要です。
伝染性紅斑は、ヒトパルボウイルスB19の感染により発症します。
このウィルスは赤血球を作ることを抑制するため、一時的に貧血を来します。妊婦さんが感染するとお腹の赤ちゃんにも感染し、赤ちゃんの貧血、そして心不全、胎児水腫を起こして亡くなることもあります。
風邪やインフルエンザと同じ様に、飛沫感染するので、マスク、手洗いが有効ですが、防ぐためのワクチンがありません。
人にうつしてしまう時期は、通常の風邪と同様の症状です。妊婦さんや身近に妊婦さんがいる方は、風邪症状の方との接触はなるべく避け、手洗い、マスクの着用をお願いします。
リンゴ病の症状は感冒様の症状と発疹(紅斑)、関節痛などですが、20%は症状がなく、50%は感冒症状のみで、典型的なリンゴ病症状は25%にしかみられません。
潜伏期間は4〜10日で、当初は感冒様の症状が多く、2週間ほど経ちウィルスが体内からいなくなってから出現するリンゴ病症状と関節痛を起こします。
典型的なリンゴ病症状の時にはすでにウィルスがいないので、この時期に他人への感染力はなくなっており、症状が出る前に感染力があるため予防には厄介な病気です。
かかったと思われる場合には血液検査でIgMという抗体が出ているか、診断が出来ます。
また伝染性紅斑はワクチンはありませんが、IgGという抗体があれば、感染の心配はありません。成人では50%くらいの方がIgG陽性です。小さなお子さんたちはこれまでかかっていないため、やはり幼稚園や保育園、小学校での流行がよくみられます。
IgMは症状が出たら保険適用で検査が出来ますが、IgGは自費検査となります。
(参考文献:産婦人科診療ガイドライン 産科編2017、2020、日本産科婦人科学会/日本産婦人科医会)
初出:平成30年11月28日
補筆修正:平成30年12月4日、6日
補筆修正:令和6年7月9日、12月5日、7日
補筆修正:令和7年1月29日、5月2日、8日、29日、6月4日、5日、10月7日、リンゴ病の報告数が増えています。