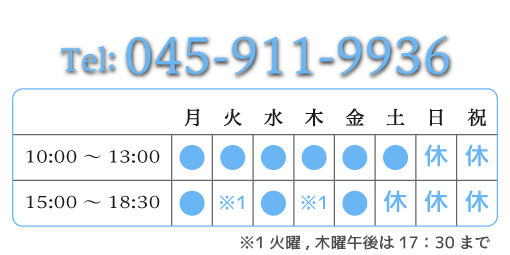ここではSTIの一つ、淋菌感染症について解説します。
この記事の目次
原因は?
淋菌感染症(淋病)は細菌の一つ、淋菌によるSTI(性感染症)です。
症状は?
クラミジア感染に似て、初期はおりものの変化、異常を自覚することがあり、進行すると下腹部の痛みとなります。
このおりもの変化やお腹の痛みはクラミジア感染よりも重いことが多く、また発熱を伴うことが多いです。
クラミジア感染と同様にオーラルセックスにより喉への感染が多く、喉の痛みを自覚します。
男性の感染も重篤で、クラミジアと同様に尿道炎、排尿時や射精時に膿が出ることや痛みが出ることがありますが、クラミジアより強い症状が出ます。
カップルのどちらかが淋菌検査で陽性となった場合、カップルでの治療が必要です。
検査方法は?
クラミジアと同様、子宮頚部への感染を疑う場合、内診で子宮頚部を綿棒でこすりますが、検査の痛みはほとんどありません。
クラミジアと同時に検査をすることが多いです。
出血しているときは菌が見つからないことがあるため、生理中、不正出血をしているときは検査は向いていません。
クラミジア感染よりも咽頭(のど)の検査で陽性となることが多く、咽頭の検査はクラミジアと同じ様に、うがいした生理食塩水を検査します。
保険診療では子宮頸部の検査と咽頭の検査を同じ日に行うことができません。
治療方法と治療効果判定
淋菌は耐性菌と言って、抗生物質に対して抵抗性があり、いくつもの抗生物質の効果がなくなってきています。
現在最も効果のある抗生物質は、セフトリアキソンで、点滴で用います。
そのため治療には院内で30〜60分の時間を要しますが、治療は1回のみです。
セフトリアキソンは、抗生物質の中でもアレルギー性が若干高く、使用できない場合もあり、その場合は他の抗生物質を使わなければなりません。
また第2選択薬としてスペクチノマイシン(トロビシン®)の筋肉注射1回もありますが、咽頭感染には効果が劣ります。
治療後はクラミジアと同様、3週間後に再検査が必要です。
STIが心配な方、喉の痛み、おりものの変化が気になる方は、早めに検査にお越し下さい。
初出:令和7年2月28日
補筆修正:令和7年4月3日、セフトリアキソンの限定出荷について触れ、治療薬スペクチノマイシンを補筆しました。