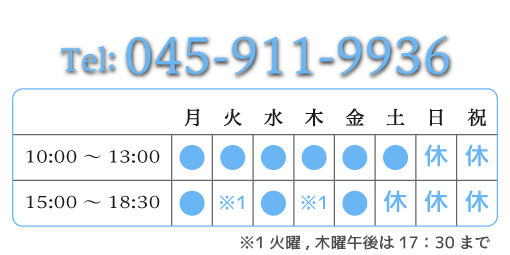2013年から2023年までの11年間の人工授精の治療成績をまとめました。

治療を受けたカップルは914で、治療周期数は3180周期でした。
治療を受けたときの年齢は上記の通りで、臨床妊娠率(子宮内に胎嚢が見えた妊娠)は 6.2%、また継続妊娠率(出産率)は5.1%でした。つまり、20周期に1名、出産する計算になります。また流産率は 17.5%でした。
右のグラフは女性の年齢別妊娠率です。カッコ内は周期数を表しています。年齢別では、30歳までの20代、30代前半、30代後半であまり違いがなく、いずれも5%前後の出産率でした。一方で41歳以降では1.2%と出産率が低下しました。
男性の年齢別妊娠率は載せていませんが、20代から50代まで、どの年代も5%前後であまり違いがありませんでした。
次は累積妊娠率と人工授精の適応別の妊娠率です。

累積妊娠率とは、回数ごとに妊娠した方を積み上げていくグラフです。OGは出産数を表します。
1回目の成績は856周期のうち63名が出産に至り、出産率は7.3%でした。2回目は642周期、出産は29名で、出産率は6.1%となります。
このように見ていくと、5回目の131名までと比べ、6回目以降はオレンジの折れ線が鈍化、9回目以降はさらに鈍化するのが見て取れます。グラフには表していませんが、16回目以降、30回目まで治療した方がいらっしゃいましたが、妊娠はされませんでした。
右は、最後に一昨年4月から人工授精が保険適応になってからの適応別妊娠率です。これは保険者になぜ人工授精をしたか伝えなければならないため、これまで以上に適応を厳密に分類しているためです。
左から機能性不妊、これはそれまでのタイミング法で妊娠しないため、ステップアップとして人工授精を選んだ場合ですが、流産例はあるものの、出産例はありませんでした。
次の射精障害・性交障害は、人工授精の最も適した適応ですが、それでも出産率は7.2%に過ぎず、次の適応はいわゆる精子現象症で、5.0%、良好運動精子数が400万未満では妊娠例はありませんでした。

以上をまとめますと、
・人工授精の出産率は5%ほど。
・女性の年齢では41歳以降で治療成績が低下します。
・適応は、射精障害・性交障害と精子減少症のうち良好運動精子数が400万を超える場合で
・いわゆるステップアップとして選択しても出産に至る方がいません。つまりタイミングがはかれていれば十分、と言えます。
・回数は、時間的に余裕があれば、5回までを勧めますが、年齢や子宮内膜症、子宮筋腫を考慮する場合、3回までとした方が良いです。
人工授精と体外受精など生殖補助医療の違いについて、こちらで解説しています。
文責 桜井明弘(日本産科婦人科学会専門医)
初出:令和6年8月14日
補筆修正:令和6年8月15日、生殖補助医療との違いについて、リンクを追記しました。