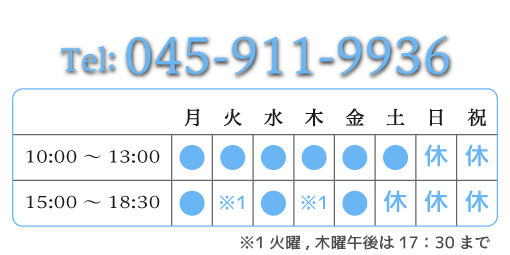乳がんの検査には、「触診」「超音波検査」「マンモグラフィー」を中心に、MRIやPET検査などもありますが、「検診」としての有効性が示されているのは、唯一、マンモグラフィーだけです。
そのため、40代以降に行われる自治体検診(対策型検診と言います)は、マンモグラフィーが用いられます。
対策型検診は、その病気が増える年代が対象となります。
子宮がん検診が20歳から対策型検診を行っているのは、20代から子宮頸がんが見られるからです。
しかし、乳癌が30代までの女性にできない、と言う意味ではもちろんありません。
日本の乳がん罹患率をグラフにしました。
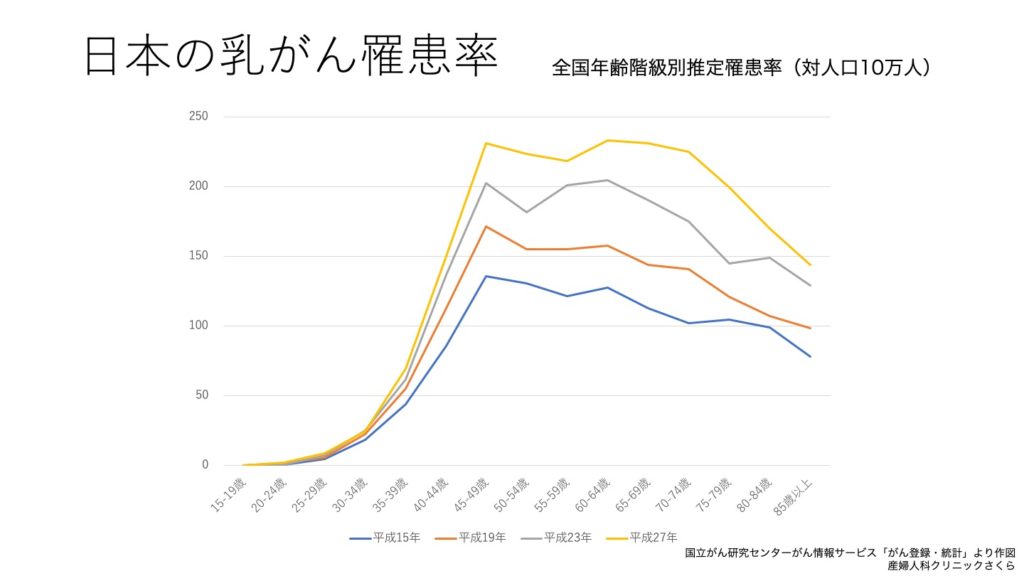
まず特徴として、
・平成15年から27年の間、全世代で乳癌が増え続けています(年を追うごとにグラフが上に向けて増えている)。
・乳癌罹患のピークは40代後半から70代前半です。
・グラフにはありませんが、日本では1年間で9万人が乳癌と診断されます。
確かにピークは40代後半ですが、30代でも、20代後半でも乳癌にかかっています。
次のグラフは20代後半、30代前半、後半の年次推移です。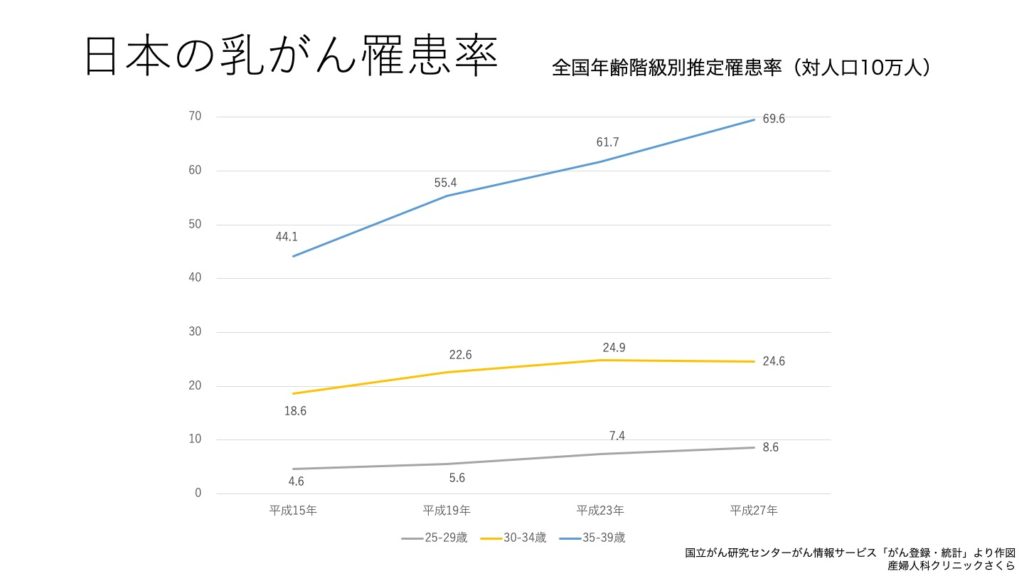
青で示した、30代後半ではこの12年間で1.5倍に増え続け、また20代後半でも2倍近くに増え続けています。
なぜ日本でこんなに乳がんが増え続けているのか、主な原因として生活様式の欧米化が指摘されています。
では、乳癌の検診として、どのような検査が行われるでしょうか。
以前より、
・触診
・超音波(エコー)
・マンモグラフィー
が行われてきました。
日本人女性の特徴として、20-30代はDense Breast(乳腺密度が高い)が知られ、欧米人と異なります。
Dense Breastでは超音波検査が検査に向いています。
超音波検査の他の特徴として、小さなしこりを見つけられることが挙げられます。
触診や、よく言われる自己検査では、1cm以下のしこりを見つけるのは難しいことが多いです。
一方で微小石灰化と呼ばれる病変はマンモグラフィーが適しており、両者の併用が最も望ましいです。
さて、芸能人などの乳癌が報道される時に、毎年きちんと検査していた、数ヶ月前に検査した時には異常が無かった、のようなエピソードが紹介され、あたかも検診の意味が無いかのように取られてしまいます。
検診ですから、異常を早期発見し、見逃しを無くすのはとても重要ですが、残念ながらどの検診でも100%見逃しがないものはありません。
検診で見逃されてしまうのはとても残念ですが、だからといって検診の意味が無い、と言うことにはならないのです。乳ガン検診
文責 桜井明弘(院長、日本産科婦人科学会専門医)
初出:令和元年11月15日
補筆修正:令和5年10月12日