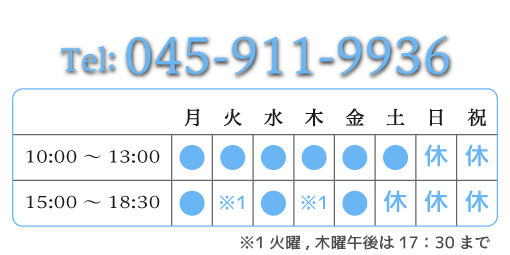腟口の左右下1/3の位置にある分泌腺が「バルトリン腺」です。23
分泌液を出す「腺」なのですが、その出口がつまってしまい、腺全体が腫れるのが「バルトリン腺嚢胞(のうほう)」。この状態では痛みはほとんどなく、違和感、異物感だけです。
バルトリン腺嚢胞の中に菌が入って感染を起こして膿が溜まったのが「バルトリン膿瘍(のうよう)」。強い痛みが生じ、また感染しているので熱を持ちます。やがて膿瘍の一部から膿が出始めることも多いです。
バルトリン腺嚢胞の状態では、違和感が強いときのみ、針を刺して内容を吸引しますが、細菌感染のリスクもあるため、症状が軽い場合は経過観察となります。
一方でバルトリン腺膿瘍では膿を吸引することが症状緩和のためにまず最初に行われます。併せて細菌の培養検査やクラミジアなどの性感染症の報告もあることから検査を行い、抗生物質を服用して、なるべく早く感染が治まるようにします。
この膿瘍は繰り返しやすい方がいます。
再発を繰り返す場合、手術的な治療方法として「造袋術(開窓術)」や「嚢胞摘出術」が行われます。
造袋術は、バルトリン腺嚢胞の一部に比較的大きな穴を開け、塞がらないようにするものです。
また「嚢胞摘出術」はバルトリン腺嚢胞をそっくり摘出する方法で、再発は起こりにくいものの、分泌液が出なくなるため、性交障害の原因にもなります。
治療はバルトリン腺のトラブルの段階や、症状に応じて決められますので、よく相談してください。
文責 桜井明弘(院長、日本産科婦人科学会専門医)
初出:令和元年12月17日
補筆修正:令和5年9月18日